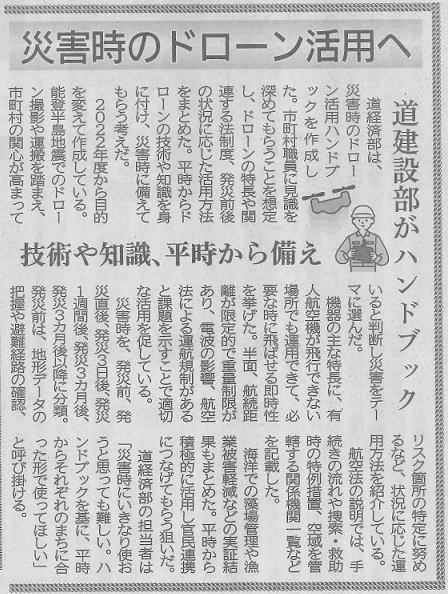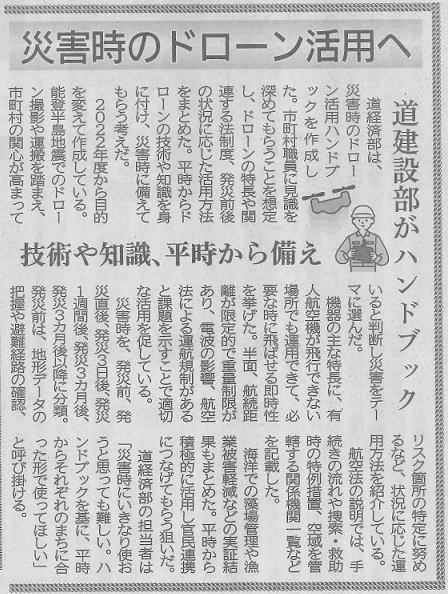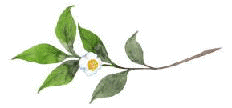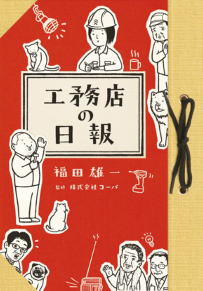令和7年5月30日
ドローンは、今では私たちの身近なものになっていますね。主に撮影に用いられることが多いと思います。人間の視覚ではあり得ない上空からの風景を見る、いわゆる空撮が可能になったことで、ありとあらゆる用途で活用される機会が増えています。一方で、犯罪もどきの使用に供されることがあるのも事実です。そのような事例を鑑み、次々とドローン飛行に規制がかかっているというのが、実情のようですね。まずは、ドローンを飛ばす地域や高さによって、国土交通省や航空局に通知をしなければならなかったり、許可を取る必要があったりと、色々な手続きがあるようです。特に飛行機の飛行ルートの範囲では、規制も厳しいと聞きました。当然と言えば当然ですか゛誰でもが好きに飛ばしていい訳ではないですよね。
建設業においても、視覚的に発注者にアピールしたり、時にはICT施工に活用するために、ドローンを使用することがあります。実際に、空撮した現場写真を職員会議の現場報告の場で目にする機会がありますが、一目瞭然とはこのこと…という感じで、視覚に訴える力は
すごいですよね。通常の現場施工に使用するばかりでなく、災害発生時にも活用できるならば、その効果は いかばかりかと…。「北海道/経済部/AI・DX推進局DX推進課」 のホームページから 『災害時のドローン活用ハンドブック』 がダウンロードできますので、内容を一読しておくのは有効だと思います。しかし、感想としては、ドローンの使用に至るまでに、こんなに手続きが沢山あるんだ~ってことに尽きます。ドローンを飛ばすまでが大変です。最近は、撮影以外の目的でドローンを使用することもあるようですから、法律を守って安全に活用してくださるようにお願いしたいですね。
← 今年の桜を、ちょっとだけ…。5月上旬に咲きました。まだまだ肌寒い日が続きますが、これから色々な植物が花開くと思うと楽しみです。
まさしく、その通り。
ちなみに、この 「春の一斉清掃」 は、ふるさとエコ&しらぬか 「自然の番人宣言」 推進事業の一環として、北海道が設定している 「道民環境の日」 に合わせて実施されたものです。
私も一斉清掃に参加したのですが、常日頃からゴミに関しては、感じるところがあります。町内のゴミステーションについて言えば、ゴミを捨てる場所に設置されている籠に、ちゃんと分別されていないゴミが、回収されずに残っていて、それがどんどん蓄積され籠の中が汚くなっていることがあります。共用している場所なので、町のごみ分別にそって捨ててほしいなぁと思います。ゴミのポイ捨てなどしないで家庭から出るゴミもきちんと分別して皆で綺麗な町、白糠町にしましょうね。
ちなみに、春の一斉清掃、ゴミ拾いが終わった後に、参加した人達の自己紹介がありました。同じ町内会でも顔も名前も知らない方もいらっしゃるのでこの自己紹介はとても良いことだと思いました。これからも町内会の行事にできるだけ参加し、色んな町内会の方たちと良いお付き合いができたらと思います。 (※恵)
5月の第二日曜日に、町内会による春の一斉清掃が行われました。前日の悪天候とは打って変わって、清々しい程の晴天に恵まれ、一気に春の陽気を感じました。午前8時30分からの一斉清掃、参加された町内会の方々とお話しながらゴミ拾いをしました。前回よりもゴミの量は少なかったように思います。それでも、最近は風の強い日が多かったので、色んな所からゴミが集まっているような印象です。なんにせよ、ゴミを外に捨てること自体間違っていますし、外出先でゴミが出たのなら、責任を持って持ち帰るとか、ゴミ箱がある施設とかであれば指定された所に捨てるなどして、あちらこちらに物を捨てることは止めましょう。4月末には 『道の駅しらぬか恋問館』 も新たな姿に生まれ変わり、連日多くの観光客で賑わっています。展望台から海を眺めているとき、はたまた海辺を歩いているときに、周辺にゴミが散乱していたら誰だっていい気持ちはしないですよね。一人でも多くの人が意識してゴミを持ち帰ったり、指定された所に正しく捨てれば、街のゴミも少なくなるのではないかと思います。春が過ぎれば夏が来て、白糠町でも様々なイベントが始まると思いますので、マナーを守って楽しい時間を共有していきたいですね。 (※咲)
この本は、とある工務店のゆるい日常を綴った4コマ漫画です。クスッと笑ってしまう場面も多く、読みやすいので、すらすら読み進めることができます。休憩中や寝る前のちょっとした時間に読むのにもおすすめです。
著者はこの本を読んだある人に、「工事現場は我々の生活のすぐ隣にあるとても身近な存在なのに、その中身はあまり知られておらず、あの 『安全第一』 と書かれた囲いの中ではこんな出来事が起こっていたのかと思うと、『不思議の国のアリス』 みたいだと思った。」 と言われたと、著者の挨拶の中で触れています。
私も安全パトロールで現場に行くことがありますが、日常の様子や、作業中の会話などは想像するしかありません。なので、この本を読んで、現場あるあるやハプニング、先輩後輩の関わり方など
こんな感じなのかなぁと、想像を膨らませています。(この本の舞台は工務店なので、弊社の現場とは違っているかもしれないのですが・・・。) いつか実際に現場で、この想像が合っているのかいないのか、確かめてみようと思います。
また、弊社Instagramでも、建設業関係の本を紹介しています。紹介している本の中には、この本のように漫画になっているものもあります。本を読むのが苦手な人でも読みやすいですので、是非手に取ってみてください。 (※麻)
弊社の次世代育成支援対策の目標のひとつに、「子や孫と一緒に過ごすため、ゴールデンウィーク、夏休み、冬休みに休暇をまとめてとれるよう指定有給休暇日を設定する」 とあります。そのおかげで、今年度のゴールデンウィーク休暇は11日間と、非常に長い休みをいただくことができました。せっかくの大型連休、息子をいろいろなところに連れて行こう!と計画を立てていたのですが、胃腸炎でダウン。私も息子からウイルスをもらって体調不良で寝て過ごすことになってしまい、(胃腸炎だけに)
消化不良のお休みとなってしまいました・・・。
そんな残念な連休でしたが、久しぶりに読書時間がとれたので、SNSで話題になっていた本を購入し、読んでみました。
お土産や野菜、海産物など、売店も充実しています。乳製品などが豊富な印象でした。地元の野菜や卵などを見つけて、チーズや魚といっしょに購入してしまいました。漁組の方がいらっしゃらないのが、ちょっと寂しい気がするのは、私だけでしょうか…。魚は購入できるので大丈夫ですけど。
手ごろなコーヒーと、小ぶりなソフトクリームが欲しいなあ~っていうのが、目下の希望です。見つけられていないだけでしょうか?追々、探してみますね。また、行ってみたいって思えるのはいいですよね。白糠町の 『道の駅しらぬか恋問館』 、皆さんも行ってみてくださいね。
(写真左) 発電機を稼働し、社内にて電気が使えることを確認します。 (写真右) 緊急時用備品、電池や土のう袋などが、保管場所に必要量在庫されていることを確認します。電池などは、有効期限も確認するといいですね。
釧路市の西隣りに位置し、太平洋を臨む白糠町に本社がある弊社は、いわゆる太平洋沖の千島海溝を震源とする地震が発生した場合、津波などの影響をもろに受けること間違いなしという立地です。津波が発生した場合、最大で海抜約20mまで水没するというシミュレーションがあるくらいです。見渡す限り、せいぜい3階建ての建物しかない町内は、ほとんどが被災するに違いありません。幸い2020年に新築した弊社社屋は、杭打ち工事もきっちり行い、ものすごく太い鉄骨で作られているから大丈夫ということを、建築途上を見てきたからこそ知っている訳ですが、それでも絶対安心というものでもありませんので、緊急事態訓練は欠かせません。
BCP (事業継続計画) に従い、5月8日(木)に、全社を挙げて緊急事態訓練を実施しました。
釧路沖震源の深さ10㎞、地震の規模 (マグニチュード7.0)、震度5強の地震が発生したという想定で、午前9時丁度に訓練開始です。まずは、パソコン等を持って
社屋屋上に避難。社内イントラネットにて安否の報告をします。実際に被災した際には、その後、本社に設けられた災害対策本部の指示のもと、発電機による電源の確保、食料・燃料調達をしつつ、被害状況の確認をして、関係官庁へ報告を入れ、被害への対応に当たります。本社での采配が不可能と思われる場合には、内陸に約16㎞入った道東道白糠IC(インターチェンジ)
にある除雪ステーションを代替え拠点として災害対応することや、関係供給者(会社) の皆さんにも連絡を取りつつ、災害対策への協力をお願いしたりするなどの手順もあります。訓練当日
総務部は、主に 発電機による電源の確保や、緊急時の水・食料・資材・備品等の在庫確認などを、工事部の職員とともに実施しました。
今年の夏は暑くなるのか、どうなのか。とっても気になる今日この頃。全国の天気予報を聞く度に、九州・沖縄は30℃近くの最高気温、北上するに従って25℃~21℃くらいなのに、釧路のみが15℃前後…と、今のところ
白糠町は涼しい日々が続いています。爽やかでいいなあ~と思う日もあれば、しとしと雨で肌寒い日もあり、いずれにしても、風景は鮮やかな緑に彩られつつあるところ。毎年、この時期の植物たちの生命力には驚かされてばかりです。
スズメやハクセキレイといった鳥たちの活動も活発になり、耕し始めた畑のあちこちが、餌を求める鳥たちの さえずりで溢れています。例年、庭のいずれかにハクセキレイが巣を作るのですが、あんまり用心深いとは思えず、ちょっと心配です。あんなに小さいのに渡り鳥で、この季節になると
ちゃんとやって来るって、どういう仕組みなのかと毎年の疑問でもあります。それぞれのテリトリーを守りつつ、それぞれの生き物が日々を営む、そういう季節です。
進級、進学、就職された皆さんは、新しい環境に慣れてきましたか?コミュニケーションが大事って、最近読んだ本に書いてありました。そしてコミュニケーションで大切なのは、質よりも頻度なのだとか。ちょくちょく、ちょっとずつ
人と会話するようにしましょうね。新人さんもベテランさんも等しく努力が必要…なのだと思います。一緒に楽しく働きましょう!
今回は、5月20日(火)の北海道建設新聞から、ドローン活用についての記事をご紹介します。
地元食材を使った料理やスイーツを楽しむことができる飲食コーナーや、隣接する 「キッズコーナー」 が人気です。長さ10.5mの大型滑り台が目を引きますね。天井が高くて、広々していますし、子ども連れの親子でいっぱいです。南面にある大きな窓からは海も間近に見えて、晴れた日は浜辺を散歩することも出来ますし、雨の日も落ち着いた感じで良いです。
待ちに待った 『道の駅しらぬか恋問館 (こいといかん) 』 が4月29日(火)にオープンしました。
国道38号と太平洋に挟まれた これまでの恋問館より白糠町庶路方面に約800mほど移動して新築されたものです。パッと見た感じ、建物の規模も大きくなっていますし、駐車場も広くなっているようです。実のところ、オープンから今までに2回訪れただけですが、どちらも雨の日だったためか、運よく駐車場に停められたという感じです。オープン当初などは、200台収容可能な専用駐車場が満車になったため、旧道の駅駐車場も臨時駐車場としたそうですね。新旧
道の駅の間を、バスを使ってお客様をピストン輸送したようでしたよ。いずれにしても、予想以上の人気で、白糠町が想定した 1日の最大来場者数 「5千人」 の2倍以上だったそうです。白糠町の道の駅ではありますが、釧路市からも
ほど近く、ちょっとしたドライブがてらに立ち寄るには もってこいです。一度にご紹介しきれないくらい、色々な要素がありますので、追々ご紹介できればと思いますが、是非みなさんも足を運んで、体験してみてくださると嬉しいです。 (※百)
緊急事態訓練は毎年実施していますので、おおよそ サクサク進行します。今年のように、新入社員がいる場合は、手順を教えつつの訓練になり、先輩職員にとっても手順を再確認できる いい機会になります。大前提として、報告・連絡するための社内イントラネットが利用可能でなければなりませんし、全職員が携帯電話を操作しながら行動することになります。色々と操作スキルも必要なんですよ。例えば、状況報告の写真を送信する場合、データ容量が問題になります。勿論
データは小さくして送る必要がありますね。毎年、写真データを小さくするアプリは何がいいか、職員間で教え合ったりしています。今年も若い人に教えてもらって、バージョンアップです。スキルに果てはありません。
最近、白糠でも小さな地震がちょくちょくあります。太平洋の千島海溝を震源とする大地震が、いつ発生しても不思議ではないとのことですが、準備をしておけば、ちょっとは安心できますよね。皆様も、心づもりをしてシミュレーションしておくだけでも、大分
心強いですよ。備えておきましょう。 (※百)
『ちょっと一息』 は、総務部がお届けする地域の情報です。
↑屋上に避難し、安否報告をします。パソコンや記録など、必要な物を持って避難します。
5.ちょっと気になる新聞記事。
4.今年度最初の一斉清掃です。
『工務店の日報』 著者 福田雄一 監修 株式会社コーバ
3.お勧めの本をご紹介!
2.新しい 『道の駅しらぬか恋問館』 がオープンしました。
1.緊急事態訓練をしました!